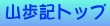| 奥穂高岳 |
|---|

笠ヶ岳クリヤ谷から(2003年9月14日撮影)
| 所在地 | 岐阜県上宝村、長野県安曇村 | |
| 白出沢登山口 | アプローチ | 神岡町から車で40分の新穂高温泉から |
| 登山口標高 | 1100m | |
| 標 高 | 3190m | |
| 標高差 | 単純2090m | |
| 沿面距離 | 片道約10Km | |
| 登山日 | 2003年10月9日 | |
| 天 候 | 晴れ、後曇り、後吹雪、後曇り | |
| 同行者 | 単独 | |
| 参考コースタイム 山と高原地図(旺文社) | 新穂高温泉(2時間)白出小屋(7時間)穂高岳山荘(50分)奥穂高岳頂上(30分)穂高岳山荘(5時間30分)白出小屋(1時間30分)新穂高温泉 合計17時間20分 | |
| コースタイム | 新穂高温泉(1時間20分)白出小屋(3時間15分)穂高岳山荘<休憩17分>(29分)奥穂高岳頂上(24分)穂高岳山荘<休憩36分>(2時間54分)白出小屋(1時間19分)新穂高温泉 合計10時間30分<休憩53分含む> | |
 クリヤノ頭に朝日があたる |
奥穂高岳に行こうと思ったのは一通のメールからだった。北ノ俣岳で一緒になった神岡の方が、その友達と毎年奥穂高岳に登っているという内容だった。奥穂と言えば上高地しか思い浮かばないが、ルートを尋ねると新穂高温泉から登ったという事だった。確かに神岡からは近い。と言うことは八尾からも近い。彼女たちは一泊だったようだが、日帰り出来ない距離でもない。雪が降る前に登ってみたいと思った。 その日は立山清掃美化大会の日で、美女平まで行く予定だった。美女平まで行っても何もないので奥穂高岳に行き先を変更する。行き先があまりにも違うので休暇届も出す。4時30分、満天の星の中、新穂高温泉へ向かう。 |
| 新穂高温泉の手前で夜が明け始める。家を出るときは星空だったのだが、ガスが所々山を覆っていて、一抹の不安を感じさせる。深山荘の駐車場に車を停めたときはすでに明るくなっていた。急いで身支度を終え、6時ちょうどに新穂高温泉へと向かう。距離にして700m、標高差60m程である。6時10分、ロープウエイ乗り場(1105m)を通過。夏は人でいっぱいだったのに、閑散としている。有料駐車場横の林道入口には鎖が張ってあった。林道をしばらく歩いた小鍋谷の橋の手前にも通行止めの柵があった。振り返ると山の頂上付近に朝日が当たっている。クリヤノ頭だろうか? |  右俣林道小鍋谷の橋の手前の通行止 |
| 2Km程歩いたところで、いったん折り返すと穂高平(1345m)に出る。そこには穂高平避難小屋がある。小屋には誰もいなかった。目の端に黒い動くものを感じて驚いたが熊ではなかった。牧場になっていて黒い牛が沢山いたのだった。霜が降りて真っ白になった草を食べていた。さらに2Km程歩いたところに白出小屋(1540m)がある。この小屋は入口に板が張られて完全に冬支度になっていた。ここからが本格的な登山道である。7時30分、登山道に取り付く。道には大きな丸い石が沢山埋まっていて、以前は白出沢の川の底だった事がうかがえる。岩の上の落ち葉が滑って歩きにくい。 |
 穂高平避難小屋 |
 白出小屋 |
振り返ればコメツガの樹林帯の合間に笠ヶ岳が美しい。奥穂高岳から見る穂高連峰、槍ヶ岳、そして表銀座の山並みを思い浮かべると自然とピッチが上がる。 8時17分、白出沢にかかる重太郎橋に到着。ここで白出沢の右岸に渡る。バタ角(三寸角)4本を束ねた長さ5m程の簡便な橋で、水量の多いときは緊張するだろう。渡りきったところから断崖を削って作られた道になる。重太郎の岩切道と呼ばれるところで鉄筋棒や鎖が張ってある。100m程続いている。それが終わると今度は天狗沢、鉱石沢のガレ場を横切る。「危険、落石多し」の看板に緊張する。 8時17分、白出沢にかかる重太郎橋に到着。ここで白出沢の右岸に渡る。バタ角(三寸角)4本を束ねた長さ5m程の簡便な橋で、水量の多いときは緊張するだろう。渡りきったところから断崖を削って作られた道になる。重太郎の岩切道と呼ばれるところで鉄筋棒や鎖が張ってある。100m程続いている。それが終わると今度は天狗沢、鉱石沢のガレ場を横切る。「危険、落石多し」の看板に緊張する。
|
 白出沢から見上げる笠ヶ岳 |
 白出沢にかかる重太郎橋 幅36cm、長さ5m |
 重太郎の岩切道 右岸の岩壁に幅50cm程の 道が続く |
 白出沢に出る少し手前に避難場所のように石垣が積んであった。後で分かったのだが、昔の荷揚げの中継ぎ小屋の跡だった。今でもここにツエルトを張れば、快適な避難場所として使えるだろう。白出沢の中央に出て、背の低い灌木の間を行くと、すぐにガレ場となる。ここから穂高岳山荘のある白出のコルまで、両側が切り立ったガレ場の直登となる。青かった空も白出沢のコルあたりから白くなり。笠ヶ岳も見えなくなってくる。ピッチを上げるが穂高岳山荘は遠い。
白出沢に出る少し手前に避難場所のように石垣が積んであった。後で分かったのだが、昔の荷揚げの中継ぎ小屋の跡だった。今でもここにツエルトを張れば、快適な避難場所として使えるだろう。白出沢の中央に出て、背の低い灌木の間を行くと、すぐにガレ場となる。ここから穂高岳山荘のある白出のコルまで、両側が切り立ったガレ場の直登となる。青かった空も白出沢のコルあたりから白くなり。笠ヶ岳も見えなくなってくる。ピッチを上げるが穂高岳山荘は遠い。
|
 途中に大きな雪渓があった。右から深く切り込んで来ているセバ谷の雪渓だ。大きなスノーブリッジを造っていた。穂高岳山荘が見えるのだが、なかなか近づかない。岩の上に積もった雪が滑り、歩きにくい。凍っている岩もあり、そちらの方が危険だった。
途中に大きな雪渓があった。右から深く切り込んで来ているセバ谷の雪渓だ。大きなスノーブリッジを造っていた。穂高岳山荘が見えるのだが、なかなか近づかない。岩の上に積もった雪が滑り、歩きにくい。凍っている岩もあり、そちらの方が危険だった。 空がガスで覆われてしまうと途端に冷え込んで来る。厚めの革手袋をしているのだが指の先が冷えて痛い。そのうち感覚がなくなってくる。袖から入ってくる風も冷たく、腕が冷えてくる。小屋は近いと思い、そのまま歩いた。 空がガスで覆われてしまうと途端に冷え込んで来る。厚めの革手袋をしているのだが指の先が冷えて痛い。そのうち感覚がなくなってくる。袖から入ってくる風も冷たく、腕が冷えてくる。小屋は近いと思い、そのまま歩いた。
|

 ガレ場の登山道はすぐに見失ってしまう。時々岩の落ちる音がするので崖に近づかないようにする。崖に近づいている登山道は敢えて歩かず、40m程の幅の沢の真ん中を歩いた。残雪期にこの雪渓を登ってみたいと思ったが落石が危ないかもしれない。10時45分、穂高岳山荘(2996m)に到着する。天候は雪に変わっていた。
ガレ場の登山道はすぐに見失ってしまう。時々岩の落ちる音がするので崖に近づかないようにする。崖に近づいている登山道は敢えて歩かず、40m程の幅の沢の真ん中を歩いた。残雪期にこの雪渓を登ってみたいと思ったが落石が危ないかもしれない。10時45分、穂高岳山荘(2996m)に到着する。天候は雪に変わっていた。
|
 小屋の前の石畳に若者が1人いた。涸沢から登ってきて又、涸沢へ降りるそうだ。この時、一瞬涸沢と涸沢ヒュッテが見えた。降りていく人も1人だけ見えた。小屋に入ってストーブで手を温める。暖かさは感じず、ただ痛いだけだった。子供の頃はそんなことはちょっちゅうだった事を思い出す。寒いのでコーヒーを注文するが、お客さんがいないからか、湯を湧かす事から始めている。アイゼンが必要かどうか訊ねると、アイゼンは必要ないがクサリとハシゴは凍っているから注意するようにとの事だった。11時2分、フリースのセーターと夏用の雨具を身につけ頂上を目指す。外はすでに吹雪に変わっていた。
小屋の前の石畳に若者が1人いた。涸沢から登ってきて又、涸沢へ降りるそうだ。この時、一瞬涸沢と涸沢ヒュッテが見えた。降りていく人も1人だけ見えた。小屋に入ってストーブで手を温める。暖かさは感じず、ただ痛いだけだった。子供の頃はそんなことはちょっちゅうだった事を思い出す。寒いのでコーヒーを注文するが、お客さんがいないからか、湯を湧かす事から始めている。アイゼンが必要かどうか訊ねると、アイゼンは必要ないがクサリとハシゴは凍っているから注意するようにとの事だった。11時2分、フリースのセーターと夏用の雨具を身につけ頂上を目指す。外はすでに吹雪に変わっていた。
|
 奥穂高岳へハシゴ場 |
 奥穂高岳へのクサリ場 |
 いきなりクサリ場が現れ、ハシゴへと緊張する道が続く。この状態が続くのかと心配したが、すぐに普通の登山道に戻った。
いきなりクサリ場が現れ、ハシゴへと緊張する道が続く。この状態が続くのかと心配したが、すぐに普通の登山道に戻った。 だが小屋に荷物をデポしたときに地図もいっしょに置いてきてしまい、方角がよく分からない。頂上までの距離も標高差も分からないまま登る。景色はガスに隠れて全く見えないが、先ほどの若者が登ったのか、かすかに足跡があるのがありがたかった。霰混じりの横風の中を慎重に登ると、いきなり目の前に祠が現れた。11時31分だった。 だが小屋に荷物をデポしたときに地図もいっしょに置いてきてしまい、方角がよく分からない。頂上までの距離も標高差も分からないまま登る。景色はガスに隠れて全く見えないが、先ほどの若者が登ったのか、かすかに足跡があるのがありがたかった。霰混じりの横風の中を慎重に登ると、いきなり目の前に祠が現れた。11時31分だった。
|
| 今田重太郎氏が積んだという3mのケルンの標高は3193mで3192mの北岳を抜いて日本第2位になる。だが人工物では正式な山の標高とはならないようで、日本第3位の山にあまんじている。西穂高岳、前穂高岳の標識に樹氷が張り付き、奥穂の頂上はすでに真冬だった。来年はこの先の前穂高岳、西穂高岳に行くことを誓い、引き返す。11時55分、小屋に戻る。寒さでビールも飲む気がせず、熱燗にする。メニューにあるラーメンも注文する。ほっとするひとときだった。 |
 入って正面の売店 |
 入って右側のロビー(太陽のロビー) |
 右側から売店方向 その左が食堂 |
 玄関から右側ロビー方向 |
| 大正13年に建てられたという穂高岳山荘は落ち着いた山小屋だった。すでに小屋終いの準備に入っていて屋内にドラム缶を並べたり、雪の重さに耐えるための予備の柱をいくつか梁に立てていた。食堂のテーブルもどこかへ運んでいた。 |
 12時31分、穂高岳山荘を後にする。雪の積もった岩で滑らないように慎重に降りる。ガスで見えない崖から聞こえるカラカラという落石の音も怖いが、音もなく落ちてきて、はじけ散る石がもっと怖かった。草付きにでもバウンドして落ちてくるのだろう。ガラ場を降りきりって、ほっとする。
12時31分、穂高岳山荘を後にする。雪の積もった岩で滑らないように慎重に降りる。ガスで見えない崖から聞こえるカラカラという落石の音も怖いが、音もなく落ちてきて、はじけ散る石がもっと怖かった。草付きにでもバウンドして落ちてくるのだろう。ガラ場を降りきりって、ほっとする。 14時36分、重太郎橋を通過し、15時23分、白出小屋に到着する。後はゆっくり紅葉真っ最中の林道を歩くだけだ。16時42分、ロープウエイ乗り場に到着。その穏やかな風景に、数時間前の真冬の世界が夢の中の出来事のように思えた。
14時36分、重太郎橋を通過し、15時23分、白出小屋に到着する。後はゆっくり紅葉真っ最中の林道を歩くだけだ。16時42分、ロープウエイ乗り場に到着。その穏やかな風景に、数時間前の真冬の世界が夢の中の出来事のように思えた。
|