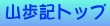| 戸田峰 |
|---|

西新山頂上から(2003年3月21日撮影)
| 所在地 | 八尾町 | |
| 小井波峠 登山口 |
アプローチ | 八尾町より車で30分 |
| 登山口標高 | 490m | |
| 標 高 | 1227m | |
| 標高差 | 単純724m 累積900m | |
| 沿面距離 | 往路6300m 復路6300m 合計12600m | |
| 地 図 | カシミール ←クリック | |
| 登山日 | 2003年3月29日 | |
| 天 候 | 雨、後曇り、後晴、後曇り | |
| 同行者 | 浜治義幸、秋元一秀、中林正勝 | |
| 参考コースタイム とやま山紀行(桂書房) | 小井波峠(240分)戸田峰(130分)小井波峠 | |
| コースタイム | 小井波峠(255分)戸田峰(180分)小井波峠 | |
|
富山平野から神通川左岸に、なだらかな三角形の山として見えるのが戸田峰である。
特別な山でもなかったのだが、いつしか、こだわりの山になっていた。その理由は昨年の12月1日の山歩記に記したとおりである。 山への思い入れというのは人それぞれなのだが、この山に関しては共通の思いがあるように感じるのである。 今回、メンバーには中林が加わり4人になった。天気予報では1日中快晴のはずだったのに朝から雨が降っていた。 朝6時15分、集合場所にはすでに浜治さん(以下敬称略)が来ていた。気合いがつたわってくる。それもそのはず、6回目の挑戦である。 6時35分、1台に乗り合わせて小井波峠に向かう。 |
 小井波峠から林道への取り付き |
 林道の片側には大小の石が転がっていた |
|
夏場なら小井波峠から、さらに林道を2Km程車で入れるのだが、冬場は峠からつめる事になる。 このところの暖かさで山がかなり黒くなっている。ひょっとしたら林道を車で入れるかもしれない、などと話しながら小井波峠に着いて見ると雪はまだ70〜80cm程あった。 7時40分、身支度を整え小雨のちらつく中、小井波峠(490m)を出発。くさった雪を坪足で歩く。少しごぼるが歩きにくいと言う程ではない。 |
 ガスの中でのコース取り |
 木の廻りの雪も溶けて春の気配を感じる |
|
1Km程入ったところでかんじきを履く。雨もあがっていた。林道の山側は斜面から落ちてきた大小の石が散らばっている。見たところもう落ちてくるような浮石は無いようなので心配もせずに歩く。だがそれほど安全でもなかったらしい。 お腹の調子が悪く、用足しをした場所が山側の穴のあいたところだった。帰る時にそこを見ると雪と小石で埋まっていた。皆に「やっている時じゃなくよかった」と冷やかされる。そんな格好で雪に埋まっていたら、まるで踏みつぶされたカエルだ。 |
 地図とコンパスで道を探る |
 ガスの中の杉林 |
|
8時50分、林道の終点近くから作業道を利用して尾根に向かう。インターネットの情報では1週間前にこの山に人が入っている。その足跡がかすかに残っていた。 874mピークで12月に来たときに付けた赤い布を確認する。ここから右に方向を変え、なだらかに下る。その後、細い尾根を登って行くと急に広い場所に出る。 ガスの中ではコンパスに頼るしかない。ここから右側の斜面をトラバースすると1002mのピークを迂回出来るハズと皆と行動を別にする。が、小さな谷があったりして自信がなくなりコースを左に取り、手前の小さなピークで皆と合流する。 |
 小休止 |
 杉の葉に付いた樹氷 |
|
この広尾根は左側を通れば間違いないようだ。やや下った後の50mの急登を登りきったところが昨年12月に来たときの最終地点となった1002mピークである。 昼食をとった杉の木と、その時に付けた赤い布も確認出来た。ここから少し下って、登りきったピークでは戸田峰が左後ろに見えるはずだが、ガスでそれも確認出来なかった。 アップダウンを繰り返しながらコースを徐々に左に取っていく。この頃からガスが切れ始める。左側に久負須川に向かって落ち込んでいるワサビ谷が見える。標高を上げるにつれ、小枝に付いた樹氷が大きくなってくる。 |
 樹氷の中をひたすら歩く |
 頂上手前の最後のピーク |
|
約60mを登り切った所が真っ白なまんまるい丘だった。頂上かと思ったが、その向こうにもう一つ山が見える。そこは1170mピークだった。ガスがかかっていたら頂上と勘違いするようだ場所だ。 見事なブナ林を登り、11時55分、頂上(1227m)に立つ。樹氷に覆われた木の枝の中に戸田峰の標識があった。記念撮影の後、風を避けて南側の斜面で昼食とする。時々青空も見え始める。 |
 頂上の看板(1227m) |
 音を立てて落ちてきた樹氷 |
|
太陽が降り注いだと思った瞬間、パラパラと光るものが落ちてきた。樹氷だった。太陽の光はこんなにもエネルギーを持っているのかと思う間もなく、周りの木々から一斉にザーっと音を立て、風に舞い上がる。 小さな水晶の破片が空を舞っているかのようだった。自然が作り出した、一瞬の出来事だった。雲が太陽を覆った瞬間、そのショーは終わっていた。 カメラのシャッターなど押さずに、その中に身を任しておけばよかったと悔む。もう2度と経験する事は出来ないかもしれないのだ。 |
 黒い杉の山が西新山で奥に大高山、左に 961mピーク |
 頂上手前のきれいなブナ林 |
| 13時40分、樹氷ショーの余韻を残したまま頂上を後にする。先週登った西新山が間近に見える。その後ろに大高山、右に唐堀山、左には小佐波御前が小さく見える。桑崎山や大日岳はかすかに見えるが剣岳は見えない。戸田峰はそんなにしょっちゅう登れる山ではない。「剱の展望台」を立ちあげた中林は残念だっただろう。 |
 頂上での記念撮影 左から秋元、浜治、中林、池原 |
 青空とブナ林 |
| 1084mのコルで浜治がカメラを落としている事に気づく。1170mピークまで戻るが見つからなかった。そのうち中林が雪面に残る何かが滑り落ちたと思われる跡を見つける。カメラしか考えられない。その跡は深いワサビ谷へ落ちている。クレパスの中などを探しているうちに、谷の途中のデブリの中にカメラがあるのを発見。1時間の探索は無駄ではなかった。降りやすい尾根から回り込んでカメラを回収する。15時5分、下山開始。 |
 ブナ林の下り |
 この右の谷(ワサビ谷)へカメラを落とす |
|
アップダウンを繰り返し16時50分、林道に出る。後は林道を下るのみだ。単調な下りに次回はスキーを持ってこようと思った。17時40分、車に到着。 帰り道、浜治は何度も言っていた。「5月に入ったら気持ちを切り替えろ」と。「何処にでも行けると思ったら間違いだぞ」と。その意味はよく解らなかったが、すぐに体験する事になるのだろう。 |
 帰りの林道から振り返った戸田峰 |
 車に帰り着く |
|
戸田という名を聞く時、いつも思い出すのは八尾高校で教鞭をふるっておられた戸田先生の事である。 後年、眼目(さっか)の立山寺(りゅうせんじ)の住職をされていた。病で退職され、八尾の祈樹寺に戻られた事を聞いてまもなく、帰らぬ人となった。一昨年の事である。 直接教わったことはなかったが、物腰の柔らかい、上品な方だった。いつまでも心に残る先達の中の1人である。 |