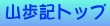| 剱 岳 |
|---|

大猫平の尾根より(2003年6月21日撮影)
| 所在地 | 上市町、立山町、宇奈月町 | |
| 馬場島 | アプローチ | 富山市より車で1時間10分 |
| 登山口標高 | 760m | |
| 標 高 | 2998m | |
| 標高差 | 単純2238m 累積(+)2268m 累積(−)2268m | |
| 沿面距離 | 片道7150m 往復14.3Km | |
| 登山日 | 2003年9月7日 | |
| 天 候 | 晴 | |
| 同行者 | 単独 | |
| 参考コースタイム 山と高原地図(旺文社) | 馬場島(4時間30分)早月小屋(3時間30分)剱岳(2時間30分)早月小屋(3時間)馬場島 合計13時間30分 | |
| 参考コースタイム とやま山歩き(シーエーピー) | 馬場島(5時間)早月小屋(3時間)剱岳(5時間)馬場島 合計13時間 | |
| 参考コースタイム 立山・剱岳を歩く(山と渓谷社) | 馬場島(5時間30分)早月小屋(3時間)剱岳(5時間20分)馬場島 合計13時間50分 | |
| コースタイム | 馬場島(3時間)早月小屋<休憩10分>(2時間)剱岳<休憩32分>(1時間45分)早月小屋<休憩12分>(2時間17分)馬場島 合計9時間55分(休憩54分を含む) | |
|
天気予報に不安があったので、剱岳に決めた。一度も行っていない笠ヶ岳や、前回、ガスで何も見えなかった白馬岳は快晴の日に登りたい。 朝2時50分に目を覚まし前日作っておいたうどんを温める。単独山行きの場合は、全て自分でやらないと誰もやってくれない。3時20分、静かに家を出る。 4時過ぎにスーパー林道を離れ馬場島を目指す。山道は真っ暗で所々ガスがかかっている。伊折を過ぎたあたりから雨も降り出し、気持ちが暗くなる。 4時半、馬場島の駐車場に車を停める。雨は小ぶりになってきていて、雨具を着るかどうか迷う。取りあえずズボンだけ履いて出る事にした。5時10分、ようやく薄明るくなった登山口に取り付く。 |
 狭そうに見える早月尾根にもこういう池があった |
 白ハゲ赤ハゲ、右上部の猫の頭のようなのが 小窓尾根のニードル |
|
奥大日岳の失敗を繰り返さないように始めはゆっくりと登る。3段になっている松尾平を越え、釣り尾根のような細尾根を渡ると急登となる。 一番先頭だと思っていたのに、1200m〜1600mあたりで何組か追い越した。皆、ヘッドランプで出発していたようだった。ヘッドランプを使えば30分も待たなくてよかったのにとも思ったが、明るくなってから出発して、明るいうちに帰るのが正しい日帰りだと、自分に言い聞かす。 残雪期には分からなかったが、途中に池があった。沢のようなところを横切ったり、1m程の細尾根もあったりで、峻険な尾根歩きと思っていたがそれ程単純でもないようだ。 天候がよくなってきたので雨具のズボンを脱ぎ、上もTシャツ1枚になる。 |
 早月小屋、その上が剱御前、左奥が別山 右奥が浄土山 |
 早月小屋前の椅子とテーブル |
|
8時9分、早月小屋に到着。手前で発電機の音がするので小屋が近いのが分かる。小さなピークに登るとやや下った先に早月小屋が見える。小屋の前に白いテーブルと椅子が置いてあり、早月尾根のオアシスのような場所である。 テーブルを借りてミニパンを食べていると小屋の主人が出てきて「ご苦労様」と言われた。恐縮して挨拶を返す。 頂上の方を見て「頂上に人が沢山いる」と言われるが全然分からない。8時19分、「帰りに又寄らせてもらいます」と言って出発した。10分間の休憩だった。 5月に来たときはここから先は池ノ谷側の雪渓のトラバースばかりだった。緊張の連続で、精神的にも体力的にも限界を感じ、2600mピークで敗退した。 その時は気が付かなかったが尾根筋の道も多いようだ。2600mピークは池ノ谷側に巻き道がある。ここから先は岩場が多くストックが邪魔だった。 くさり場も多いが、くさりは道しるべとして、岩を頼りに歩いた方が安全だと思う。鎖に頼り過ぎると体が安定しない。足場が遠いところにはボルトも打ってあり、危険なところはなかった。 |
 左からマッチ箱ピーク、小窓の頭、小窓の王 その手前のピークは剱尾根の頭? |
 カニのハサミ |
|
2700m辺りで金沢の超人早川さんとすれ違う。挨拶をしたが下りるのに夢中だったようだ。タイツの上にさらにサポーターをつけて両ストックで下りて行った。 帰りに早月小屋で聞いた話では、朝4時頃に馬場島を出て剱岳を往復しているとの事だったが、彼のホームページでは魚津(海抜0m)からの往復だったようだ。 上がるにつれ、徐々に呼吸が乱れてくる。疲れからなのか、3000mの高所からなのか?多分その両方なのだろう。 別山尾根との分岐点の白い標識が見えてくる。慌てず、呼吸を整えながら、10時20分、頂上に立つ。休憩を含め5時間10分で登った。 頂上ではいきなり可愛い外人女性が出迎えてくれる。(向こうは出迎えたなどとは思っていない)40人ほどが、たむろしていた。取りあえずビールで乾杯する。雲海の上に後立山連峰が横一直線に並んでいる。右の薬師岳から左は朝日岳まで見える。さらに左には毛勝三山が雲海に浮かぶ孤島のようだ。 |
 200m置きにある最後の2800mの標識 |
 頂上のにぎわい 40人ぐらいがたむろしていた |
|
ビールを飲みながら眺めているうちにかすかに富士山が見えるのに気づく。近くにいた女性に「富士山が見えるよ」と教えた。その人はすでに知っていたようで「そうですね」とやさしく答えてくれた。 八ツ峰の向こうに見える赤い屋根の小屋は池ノ平小屋だろうか? 先ほどまで見えていた鍬崎山が雲海の下に隠れ大日岳も孤島のようになっていく。いつまでいても切りがない、10時53分、頂上を後にする。 ビールが効いているのか、降りなのに息が荒い。急な岩場なのでストックを束ねて、右手、左手と持ち替えながら岩に捕まりながら下る。 2800mあたりから右膝が痛み出す。膝のクッションを使って下りるなどと言うのは疲れていないときに出来る芸当だ。疲れているときは、ゆっくり下りるか、ストックを有効に使うかの二つしか方法がない。 |
 奥に毛勝三山、手前に赤谷山、白萩山 |
 手前に八峰、奥に鹿島槍ケ岳、爺ガ岳 |
|
我慢の下りで、12時38分、早月小屋に到着。缶ビールを買って、おつりをもらった途端、目眩がした。気が付いてみると両腕が痺れている。後頭部も痺れている。ふらつくので小屋の入り口でそのまま休ませてもらった。 何だったか分からないが初めての経験だったしびれは取れなかったが気分は直ったので外へ出てビールを飲む。小屋の主人にピークの名前を教えてもらった。 知っていたのはマッチ箱ピークぐらいなものだった。ニードルと言うのはこちらから見ると猫の頭のようだが小窓尾根を下から登ると本当に尖って見えるそうだ。 冬は小窓尾根も登る人が多いそうだ。北方稜線は夏は難しいが、冬はそれ程でもないと言っていた。ならば冬に北方稜線を登ってみたいと思った。 |
 中央に雄山、右に黒部五郎、手前が剱沢 |
 左に針ノ木岳、スバリ岳、右に燕岳、 中央に唐沢岳、スバリの左に富士山が見えた |
|
12分の休憩後、12時50分、早月小屋を出発。痛む膝をかばいつつ下りる。時々登山者とすれ違うが、早月小屋泊の人達だろう。夜行で来たので眠くてしょうがないと言いながら登っていった人もいた。 雲海の下に入ったのだろう、日差しがなくなったのがありがたかった。道は登りの時よりも下りの時の方が急に感じる。足の届かないようなところもあるが、どうやって登ったのだろう? いつもは軽やかに下りるのだが疲れていると下り方も格好悪くなるようだ。ふらふらになりながらも、ようやく松尾平に出る。その手前に大きな杉の木があり、大きい方の直径が5mぐらいありそうだった。 穏やかな坂道を小走りに走ってみる。膝は大丈夫そうだ。最後の急坂を下りきって、15時5分、登山口に到着。 |
 いつも思うのだが登山者の雰囲気がない 風格なんて100年先の話だ |
 2500mあたりから見た早月小屋 |
|
駐車場までゆっくりと歩いた。道端に車を停め、談笑している夫婦。テントを張ってキャンプをしている家族。のどかな風景が心の中に溶け込んでくる。 車のドアをあける、リュックを車に積み込む、登山靴を脱ぐ、いつもの何気ない動作の全てが安らぎの中にある。この山行きの充実感と白馬岳に登ったときに感じた虚脱感との違いは何処からくるのだろう? |