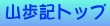| 鍬崎山 |
|---|

瀬戸蔵山から(2004年3月13日撮影)
| 所在地 | 富山県上新川郡大山町 | |
| ゴンドラ登山口 | アプローチ | 富山市より車で50分 |
| 登山口標高 | 1188m(ゴンドラ山頂駅) | |
| 標 高 | 2090m | |
| 標高差 | 単純902m 累積1090m | |
| 沿面距離 | 5.4Km | |
| 登山日 | 2004年3月13日 | |
| 天 候 | 晴後曇り時々雪 | |
| 同行者 | 単独 | |
| 参考コースタイム とやま山歩き(シーエーピー) | 山頂駅(40分)瀬戸蔵山(40分)大品山(3時間30分)山頂(2時間分)大品山(1時間10分)山頂駅 | |
| 参考コースタイム 富山県の山(山と渓谷社) | 山頂駅(1時間分)大品山(3時間)山頂(1時間30分)大品山(1時間30分)山頂駅 | |
| コースタイム | 山頂駅(24分)瀬戸蔵山(34分)大品山(2時間51分)頂上(1時間52分)<休憩30分>大品山(49分)粟巣野スキー場(15分)山麓駅 | |
|
前回、鍬崎山に登ったのは昨年の4月27日だった。頂上近くの積雪が少なくて夏道が出ているところが多かった。次回、登る時は3月にしようと思ってから1年、今はその3月である。 ゴンドラの始発は8時半なので7時に家を出る。ゴンドラの駅に着いてゆっくり身支度する。チケットを買うときに入山届けを書くよう言われる。 入山届けは書いたものをそのまま綴じていくだけのものだ。過去の入山届けを見ると、書いている人は少ない。大品山から粟巣野スキー場へと降りる人はほとんどスキー感覚なのだろう。スキーやボードを使わない人達だけが届けを出しているようだ。 行き先はほとんどが大品山であり、鍬崎山までチェックしてあったのは1組だけだった。私がこの冬2組目(単独だが)の登山者となる。 |
 山麓駅でゴンドラの運転を待つ |
 山頂駅 今日は誰も山に登らないようだ |
|
ゴンドラは定刻に運転開始となる。山頂駅から少し離れた高台でかんじきを履く。リュックの中にはアイゼンがあり、リュックの外には山スキー(フリートレック)が括られている。車の運転中にピッケルを忘れたことを思い出したが取りに帰っている時間はなかった。 8時50分、ピッケルを持たない不安はあったが、かまわず出発する。他には登山者は誰もいないようだ。雪は堅く、かんじきは必要なかった。途中で振り返ると、300m程後方から追いかけてくる者が1人いた。 9時10分、瀬戸蔵山に到着。後ろから来る登山者を待っていようかと思ったが、とりあえずそのまま歩を進める。 |
 瀬戸蔵山のアンテナ 誰か1人後を追ってくる者がいたが |
 大品山の広場 足跡が沢山あったが 皆、粟巣野へ降りて行っていた |
|
坪足の足跡が続いている。人数は5〜10人ぐらいだろうか? 雪面は堅いので足跡のない歩きやすい所を選んで歩く。 途中の急登で蹴りこみを入れながら登ろうとするが、堅くてかんじきでは歯が立たない。踏み跡を拾いながら登る。振り返るが後を追ってくる者は見えない。 9時48分、大品山に到着。軽く水分補給をすませ、鍬崎山に向かう。 まっすぐに降りると和田川へと向かってしまうので、尾根の左側(北側)に沿って降りる。何故か金剛堂山のりゅうこ峰の降りも白木峰の仁王山の降りも皆、左側の灌木のすくない部分がコルへ降りる正しいコースになっている。不思議な偶然の一致だ。 |
 大辻山と美女平 |
 大品山から二つめのピークの登り |
|
最初のピークを登り切ったところでかんじきからアイゼンに履き替えた。スキーもブナの木の陰にデポして荷を軽くする。大品山までの登り返しに持って降りたスキーを又、持って登るのはシャクだが、人気の大品山においてくる気にはなれなかった。 振り返ると大品山の手前側に一人の登山者が見える。足跡を追ってきたようだ。手を振ったが気づいたのか気づかなかったのか、そのまま引き返していった。 山の中にいきなり一人、取り残されたようで、一瞬の孤独感に襲われた。覚悟の上でのことなのに、なまじっか人が追ってくるから人恋しくなってしまうのだ。 改めて単独であることを肝に銘じる。 |
 その二つめのピークは複雑な格好をしている 尾根が三つに分かれているので降りでは注意 |
 鍬崎山は北側に向かっての雪庇が多い |
|
第二のピークを登り切ったところは複雑な格好をしていて中が盆地のようになっている。上から見るとなだらかな尾根が三つに分かれている。視界の悪い時の降りでは注意が必要だ。 第三のピークへの登りは一番長い急登で35度ぐらいの斜面が150m程続く。ここも降りでは注意が必要な所で、尾根らしい所を降りると和田川へ降りていってしまう。北西方向ではなく北向きに降りなければならない。 青空は消え、徐々に風が強くなる。明日は仲間と猿ヶ馬場山に登る予定なので体力も温存しなければならない。なんとなく気分が盛り上がらない。 |
 雪庇は大きくて上で相撲を取っても大丈夫? |
 尾根の登りも雪庇状になっている所がある |
|
第三のピークあたりから、雪庇が大きくなってきて、それにも注意をはらう。幅3m程しかない細尾根が雪庇だけで出来ているようなところもあり、緊張しながら登る。 昨年、大きな岩と雪がキレット状になっていた所は雪で埋まっていてカモシカの足跡があった。垂直に近い壁だがカモシカも細尾根のここしか通るところはなかったようだ。 このあたりからビレイヤーが欲しいと思うようになった。この時期に1人で来る山ではないようだ。 |
 この下は大きな岩だったはず(昨年の記憶) カモシカの足跡だがここしか登る道はない |
 雪庇だけで出来ているような細尾根の急登 (降りるとき撮影) |
|
アイスバーンではストックは全然刺さらない。ピッケルが欲しいと思ったところは何回もあった。アイゼンの前の爪2本で登ったところもあった。だが最後の頂上直下の右下がりの斜面が一番怖かった。木も生えていないツルツルの斜面が谷底に消えている。 アイゼンの左側の爪だけでトラバースぎみに歩く。ストックは刺さらないので2本束ねて左側の支点とする。滑るか転倒したらお終いだ。何度も引き返そうと思いながらも登り切ってしまった。帰りが怖い。 |
 頂上直下の右下がりのアイスバーンの斜面 ピッケルを忘れてもっとも怖かったところ |
 樹氷と言うほどきれいではないが... 頂上前後の3時間程は風が強かった |
|
12時40分、鍬崎山頂上に立つ。頂上の標識は半分程雪面に頭を出していた。この頃が一番風が強いときで雨具をウインドブレーカー代わりに着る。気温は氷点下7度だった。 立山連峰や薬師岳は雲に隠れて見えない。東南の方向に真っ白に凍った有峰湖が見え、宝来島が黒く浮かんでいる。その右には鉢伏山がその長い尾根を北に伸ばし、どっしりと居座っている。 寒くて乾杯する気にもなれず10分後の12時50分、下山開始。寒かったが、もしもの時に備えて滑りやすいウインドブレーカーを脱いでセーター姿で降りる。最初から左下がりのアイスバーンで登りの時よりも慎重に歩を進める。細尾根を降りきるまで緊張の連続だった |
 半分出ていた頂上の標識 遠くは薬師岳の裾 |
 真っ白に凍った有峰湖と宝来島 |
|
降り始めた頃からガスがかかり出し雪も降り出す。3番目のピークからの降りで尾根を間違えて和田川方向へ降りそうになる。ここは尾根通りに降りると間違いで、右側の斜面を降りるような感じでちょうどいい。 第2のピークの複雑な尾根を超え、第一のピークに戻りほっとする。デポしたスキーを回収し、恒例の一人乾杯! ガスに煙る木々の間に雪が舞い降りていた。 |
 頂上から東に延びる尾根 奥に見えるのは 薬師岳の裾野 |
 風と吹雪に見舞われた頂上から降りてきて 大品山からスキーで粟巣野に向かう |
|
14時、コルへ降り、大品山へと登り返す。大品山で本日始めてスキーを履いた。たくさんのスキー跡があり、迷うことなく粟巣野スキー場に向かう。 貯水池の上部の細尾根ではほとんどの人がスキーを脱いで坪足で降りていた。かまわず横滑りで降りる。導水管の横を通り粟巣野スキー所に降り立った頃、天候は回復していた。 来年は2月にチャレンジしたいと、ふと思った。だが2月に単独で日帰り出来る自信はない。一緒に行ってくれるタフな仲間を見つけないといけない。 |
 粟巣野スキー場の上にある貯水池 水量はかなり減っていた |
 粟巣野スキー場 降りてきた頃に風はやんで、いい天気となった |