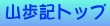| 小佐波御前山 |
|---|

小佐波御前山登山道途中から(2004年12月18日撮影)
| 所在地 | 上新川郡大山町 | |
| 今生津登山口 | アプローチ | 富山市から41号線を南下して楡原から橋を渡り今生津から |
| 登山口標高 | 142m | |
| 標 高 | 754m | |
| 標高差 | 単純612m | |
| 沿面距離 | 3.4Km | |
| 登山日 | 2004年12月18日 | |
| 天 候 | 曇り時々雨 | |
| 同行者 | 山の神 | |
| コースタイム | 今生津登山口(1時間52分)小佐波御前山頂上<休憩52分>(58分)今生津登山口 | |
|
秋山でもなく冬山でもない時期に登られる山は限られている。その中の一つが小佐波御前山だ。もっともこの山は雪山でもよく登られている。登山口が猿倉スキー場なので雪が降ってもアプローチが楽だからだろう。 熊よけに山の神を誘う。二人の方が色々と騒がしいはずだ。一人だと会話さえない。 |
 大沢野町今生津集落からの登山口 |
 舗装道路から左へ分岐する(分かりにくい) |
|
今年の1月に頂上から裏側(楡原側)に降りようとして道が分からず断念したことがある。低山とはいえ夏道を知らずに降りるのは怖い。 地図にも載っていないので車を走らせながら登山口を探す。今生津の部落で聞くと部落のすぐ横が登山口だった。一部、生活道路でもあるようだ。 駐車場を聞くとどこかその辺に停めていけとのこと。道路脇に車を停めて身支度を終え、10時33分、登山口にとりつく。 舗装された道は車が入れるほど広い。実際、途中に車が停まっていた。10台は駐車できるような広場もあった。車で入った方が道路上に停めるよりはよかったようだ。 |
 このポールに書いてある「行って来い」とは? |
 途中にあった水田の跡? |
|
舗装道路の終点近くで左に入る歩道がありちょっと迷った。だが部落の人の話では、ふるさと遊歩道は頂上まで一本道で迷うようなことはないとの事だったので舗装された道を進む。 未舗装になった部分からやや荒れた道のように見えたが疑わず登る。実はこれは失敗だった。 杉林の中を東に向けてジグザグに登る。牧線48号とか47号とか書いてある標識は何だろう? 標識の支柱に「行って来い」と書いてあったのはいったい何だったんだろう? |
 「久庵」と書かれた別荘があった |
 別荘横の離れにはソファーが置かれていた |
|
夏草が生えていたら多分分からないだろうと思われるような道を行く。田の畦のようなところや用水跡のようなところを歩いていると東西に走っている広い道に出た。 トラクターぐらいなら走れそうな広い道である。これが正しい登山道だった。とにかく合流できてよかった(^_^) しばらく登ると道が左右に別れていた。きれいな左側の道を選びゆっくり北側に方向を変えると水田跡らしい所に出る。沢はせき止められて池になっていて、その上部に「久庵」と書かれた山小屋が建っていた。奥に離れも建っている。 大きなガラス戸の離れの中にはソファーとテーブルが置かれ、オールドの瓶が2本置いてあった。誰かが週末の一時をここで過ごしているのだろう。 |
 山平(さんでら)部落跡 |
 分水槽か? |
|
その小屋の横を通って登り切ると平らな場所にでる。木柱に「山平部落跡」とある。戦後は30戸もあったといわれる集落跡である。 昭和初期に水害(床上浸水)にあったそうだが何処からそのような水が流れてきたのだろうか。昭和43年の廃村時には4戸しかなかったそうだ。 廃村跡にたたずんでいると、やむなく村を立ち去った人たちの無念さが伝わってくるようだ。晩秋のこの季節にはなおさらその感が強い。 |
 人の住んでいた痕跡ははっきり残っている |
 右は芦生へ左は今生津の分岐点でもある |
|
この集落跡から西に向かうと芦生集落に降りるようだ。ここから御前山の裾にそって沢の右岸を歩く。方向は東南東だ。 その沢を横切ると又、右側に涸れ沢があり、その涸れ沢の右岸を辿るといよいよ山道らしい登りとなる。やがて涸れ沢を横切り南に向かう。 ジグザグに登っていくと小佐波御前山の南尾根に近づく。尾根から20〜30m程のところから左にトラバース気味に北に向かう。 |
 前方に小佐波御前山の前衛峰が見える |
 山懐から徐々に登山道らしくなる |
|
200m程行くと尾根に出る。頂上近くに松の木が一本見えるので積雪期のいい目印になる。いったん軽く降り、右に黒川を望みながら尾根を登り切ると松の木の横に出る。 ここから左下がりのなだらかな尾根を北に100m程で頂上近くの石版の裏側あたりにたどり着く。その石版の手前にトイレが建っていた。分かりにくい場所なので広場のどこかに看板か標識が欲しいところだ。 |
 頂上にあるトイレ(今まで知らなかった) |
 頂上近くの広場 |
|
12時25分、頂上付近の広場に到着する。天候がよくないので皆、山登りは控えたのだろう。広場にも小屋にも誰もいなかった。 小屋の玄関には鍵がかかっていて、ぶら下がっている段ボール紙に冬季は裏から入って下さいと書かれていた。 雨戸がしめられているので中は暗い。小雨がパラついていたので使わせてもらうことにした。半分に分けた缶ビールでのどを潤し、久しぶりのカップラーメンを作る。 入り口の戸を開けたままだったので(暗かったので)食事をとっている間中、臭いに誘われて熊が入ってこないか心配だった。入ってこられたら逃げ場がない。 |
 頂上近くの避難小屋(休憩小屋) |
 冬季間は裏から入る |
|
誰もいない晩秋の里山というのも寂しいものである。誰にも会わないまま13時17分、頂上を後にする。積雪期にトレースがなくても降りられるように地形と方向を頭にたたき込む。 まず松の木に向かって尾根沿いを南下する。松の木から降りとなり、さらに尾根沿いを南下する。やや登り返したあたりで右側(西側)の斜面をトラバース気味に降るのだが、尾根からはあまり離れない。 200m程行ったところから鍋底のような谷に向かって西斜面を降る。夏道を辿るならジグザグのはずだ。沢に近づいたら北側に向かい沢を越える。 沢を越えてからは御前山の裾に沿ってトラバース気味に西側に降る。鍋底に降り立ったら左に沢を見ながら北西に向かう。 やがて沢は左に消えていき、右側から新しい沢が現れる。これを渡り少し降ると又、平らな場所に出る。そこが「山平」部落跡である。 標識があり、右に行けば芦生と書いてあるが道があるかどうかは不明。左に(南に)曲がり沢に降ると別荘(山小屋?)が建っている場所だ。 そこからは幅1mぐらいのわかりやすい道となり、やがて舗装道路に出る。舗装道路を200mほど降ると今生津集落だ。 以上が今生津(芦生)登山道を降るときの概略だが、歩いてみないと分からないだろう。基本的に西に降るのだが実際には南に向かったり北西に向かったりと大きく蛇行している。 積雪量が豊富なときはまっすぐに降りた方が早いかもしれない。迷っても下に降りれば必ず車道があるのでそれほどの心配はいらない。 |
 下山中に眺めた別荘と離れ |
 登山口に帰り着く |
|
14時15分、今生津集落に降る。時間も早いので大沢野のウインディーに寄って風呂に入いった。 1階のトレーニングコーナーで体力測定をしてもらう。体重計のようなものに乗り、両手に受話器のようなものを持っただけで体力が分からしい。 体を5カ所(胴体、右手、左手、右足、左足)に分けて皮下脂肪、内臓脂肪、水分などを計り、診断してくれる。診断結果だが、皮下脂肪、内臓脂肪とも低く、上腕の筋肉は強いが、足の筋肉が標準以下との事だった(^_^;) どのあたりを標準と言うのだろう...あまり信用しないことにする。 |
 カシミールに書かれた登山道は途中が書かれていないのと尾根からの降りの一部が間違っていた。 又、山平部落跡から芦生への登山道は予想図である。12月25日に芦生から歩こうとしたが道が悪く断念した。 |