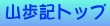| 焼 岳 |
|---|

梓川から見た焼岳(2004年7月4日撮影)
| 所在地 | 上宝村、安曇村 | |
| 上高地登山口 | アプローチ | 河童橋より徒歩で30分 帝国ホテルより徒歩で10分 |
| 登山口標高 | 1495m | |
| 標 高 | 2399m(北峰)本峰(2455m) | |
| 標高差 | 単純904m 累積950m 降り△810m | |
| 沿面距離 | 登り3.6Km 降り3.2Km | |
| 登山日 | 2004年7月4日 | |
| 天 候 | 晴れ | |
| 同行者 | 単独 | |
| 参考コースタイム 槍・穂高(山と渓谷社) | 上高地登山口(2時間30分)新中尾峠(1時間5分)焼岳頂上(2時間)中ノ湯登山口 合計5時間35分 | |
| 参考コースタイム 山と高原地図(昭文社) | 上高地登山口(2時間10分)新中尾峠(1時間10分)焼岳頂上(2時間10分)中ノ湯登山口 合計5時間30分 | |
| コースタイム | 上高地登山口(1時間27分)新中尾峠(58分)焼岳頂上<休憩40分>(1時間20分)中ノ湯登山口 合計4時間25分<休憩40分含む> | |
|
1年ぶりに焼岳に向かう。昨年は5月だった。中尾から登ったのだが雪渓が残っていて道を間違え、藪こぎまでやらされた山行きだった。 趣向を変えて上高地から中ノ湯への裏側のコース(本当は表側だと思う)で登ることにした。上高地はマイカーが乗り入れ禁止なのでバスを利用しなければいけないなどちょっと面倒である 朝4時半に家を出発し、国道41号線、471号線を経て平湯温泉に入った。 バスターミナルで駐車場を確かめ、1Km程離れた安房峠側にある「あかんだな駐車場」に車を停める。 有料で500円だった。ここから平湯のバスターミナルまで無料のシャトルバスが出ている。 |
 平湯温泉 村営あかんだな駐車場から送迎用 バス停への階段 |
 ピストン輸送されている無料のシャトルバス |
|
平湯のバスターミナルの自動発券機で乗車券を買う。上高地まで1050円だった。すぐにバスが出る。 時間は決まっていなくて、お客さんの様子を見ながら随時出しているようだ。完成まで33年もかかったという安房トンネルを3分で通過する。 帝国ホテル前で降りた方が登山口に近いのだが、上高地まで入る。上高地は30年程前に槍ヶ岳から降りてきた時、五千尺ホテルでコーヒーを飲んだ記憶があるだけである。せっかくなので見てみたいと思った。 7時に上高地のバスターミナルに着く。30名ほどいた乗客のうち登山の格好をしていたのは自分だけだった。 梓川左岸の遊歩道を河童橋へと向かう。 |
 平湯温泉バスターミナル |
 朝日に煙る河童橋と梓川 唐松の緑が美しい |
|
河童橋を渡り、梓川の右岸に渡る。河童橋を歩いている人達は昨夜からの泊まり客のようでのんびりと歩いてる。 朝日が透けて見えるような唐松の緑と、川底が水色に輝く梓川の清流とあいまって、これが本来の河童橋だと思った。 7時8分、河童橋から右岸の遊歩道を焼岳へと向かう。途中に旅館がいくつもあり、散策の人達とすれちがう。そのゆったりとした雰囲気に山登りに来たことを忘れそうになる。 |
 河童橋右岸 |
 朝日を浴びる焼岳と梓川 |
|
車道の他に梓川沿いに歩道があるのでそちらを歩く。やがてその道が合流したところにウエストン碑がありそこからは車道だけになる。 ぼーっとしたまま歩いていて、あやうく登山口を見逃しそうになった。7時50分、気持ちを切り替え、登山口に取り付く。 高度差のない樹林帯の中を行く。新しい足跡があり、何人かは先行しているようだ。バスの運転手に熊に注意と言われたが大丈夫のようだ。 |
 梓川の清流と唐松 |
 見落としそうになった登山口 |
|
徐々に斜度が出てきて標高を稼ぎ出す。左手に崩れた沢が見え隠れするようになると焼岳のドームが見えるようになった。 振り返ると霞沢岳の下に大正池が見える。池とは言っているが、こうしてみると川幅の広い川でしかない。 さらに登ると前面に岩壁が立ちはだかってくる。抜け道はないように見えたが、左側にアルミのハシゴを二つを繋げて上へ抜ける道があった。 ドキドキしながら登って来だけに、ちょっとがっかりしてしまった。 |
 もうほとんど池とは言えない大正池 |
 岩壁にかかるアルミ製のハシゴ |
|
岩の上へ抜けてからは草原となり、ジグザグの道を何回か折り返すと新中尾峠だ。時間は9時17分だった。 峠には青い屋根の焼岳小屋がある。小さな小屋だが焼岳では貴重な休憩所、避難場所となっているようだ。昨夜は17名程泊まっていたと管理人が言っていた。 峠は四つ辻になっていて中尾温泉、西穂高、焼岳へと道を別けている。左にコースを取り、焼岳展望台へと向かう。 展望台からいったん中尾峠へと降る。以前はこの峠が信州と飛騨を結んでいたそうだ。今では信州側の道が消えてしまってかすかに踏み跡が見える程度である。 |
 焼岳小屋のある新中尾峠 |
 中尾峠から見上げる焼岳のドーム |
|
中尾峠からはガラ場の直登となる。上からの落石に注意する事も大事だが自らも落石を起こさないように注意しなけれいけない。幸いこの日は上にも下にも誰もいなかった。 頂上近くの鞍部に出ると直ぐ右にガスの吹き出しが見える。硫黄を含んでいるようで周りが黄色くなっている。 その下を巻いたところが焼岳の頂上(北方)だ。10時15分、焼岳の頂上に立つ。 |
 北峯登山道ちかくの噴煙口 |
 北峰から見下ろした焼岳のお釜 |
|
頂上には十数名がいた。まだ時間は早いが食事を取っている人が多い。ここでもラーメンは人気のメニューのようだ。 期待していた雪渓がなかったので缶ビールを冷やすことが出来なかった。生暖かいビールを飲みながら小さなクーラーボックスを買う事を誓う。 お昼が近づくにつれ、徐々に人が多くなる。関東に近い山ほど若い人が多いように思うのは気のせいだろうか? 若い2人連れが新鮮に見えた。 |
 遠くに笠ヶ岳と若い登山者が二人 |
 中央が手前から西穂と奥穂、右が前穂、左が槍 |
|
穂高連峰が一列に連なって見える。手前から西穂高岳、奥穂高岳が並び右に前穂高岳、そして左奥にちょこんと槍ヶ岳だ。 西穂山荘や新穂高ロープウエイの山頂駅も間近に見える。 40分の休憩後、10時55分、頂上を後にした。 |
 中ノ湯温泉のほうへ下る |
 この看板を見ながらコースを間違えてしまった |
|
鞍部から右に折れ、中ノ湯温泉の方へ降る。こちら側にも噴気口があり、盛んに噴煙を上げていた。 歩きやすいとは言えない道だがダブルストックで快調に標高を下げる。が、快調にとばしすぎて分岐点を通り過ぎてしまった。その標識をカメラに納めながらである。 かなり降ってから変だと思ったがすでに手遅れだった。途中で追いついた家族に訪ねると、分岐点はずっと上だとの事。がっくり来たが登り返すのも嫌で、車道を歩くことにする。 12時15分、中ノ湯温泉の登山口に出た。ここから安房峠越えの車道を歩くことになる。 この車道が長く、なかなか標高が下がらない。最初に第10カーブがあり、折り返すごとに第9、第8と減っていく。 アスファルトの道は照り返しが強く、ましてや道を間違えての歩行というのは精神的にも辛かった。 第6のカーブでいい加減嫌気がさしてきたところで中ノ湯温泉のマイクロバスが止まってくれた。地獄で仏と思えるほどありがたかった。 |
 貸切が原則らしい「ト伝の湯」 700円 |
 5〜6人も入ればいっぱいの洞窟の湯船 |
|
中ノ湯のバス停まで送ってもらう。そこは上高地への入口であり「ト伝の湯」があるところである。売店で700円を払い、鍵を受け取ってお湯に入る。 中は洞窟になっていて電気を点けないと何も見えない。湯船は5〜6人、洗い場は2人しか入れそうもない。1人ではもったいないような貸切の秘湯だった。 中ノ湯から平湯温泉まではバスであっという間である。平湯温泉のバスターミナルのレストランで昼食をとり、帰り道、いつもの喫茶「ウインディー」でくつろぐ。 単独行の時はもう少し距離のあるハードな山を選ぼう、と思いながら富山へと車を走らせた。 |