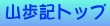| 五色ヶ原(敗退) |
|---|

龍王岳より鬼岳、獅子岳、五色ヶ原を望む(2005年6月26日撮影)
| 所在地 | 富山市?立山町? | |
| 室堂登山口 | アプローチ | 立山黒部アルペンルート |
| 室堂標高 | 2430m | |
| 五色ヶ原標高 | 2490m | |
| 標高差 | 単純60m 往復累積(+)1750m | |
| 沿面距離 | 往復14Km | |
| 登山日 | 2005年6月26日 | |
| 天 候 | 晴 | |
| 同行者 | 単独 | |
| コースタイム |
室堂(1時間7分)龍王岳(57分)鬼岳東尾根<休憩20分>(36分)浄土山<休憩48分>(1時間)室堂 合計5時間<休憩1時間8分含む> | |
|
ふと五色ヶ原まで行ってこようと思った。アルペンルート営業再開日の4月10日以来、2回目の立山である。2週間、沢に向かっていたせいか久しぶりの山という気がした。 室堂から薬師岳方面は30年前に歩いたきりでほとんど記憶にない。確か、弥陀ヶ原ホテルで午前中に勤務を終え、午後から向かったはずだ。夕方には五色ヶ原の小屋に着いている。 |
 室堂から一ノ越方面へ向かう |
 姥堂から右にコースを変える |
|
6時40分のケーブルで美女平に向かい、7時のバスで室堂に向かう。室堂には7時50分頃着いた。屋上に出て身支度を終える。 8時ちょうど室堂を出発。まもなく7月に入ろうとしているのにいきなりの雪上歩行である。今年は雪解けが遅い。 祓堂から右にコースを変え龍王岳へのコルに向かった。雪渓が残っているので一ノ越をパスしてのショートカットだ。 |
 一ノ越から龍王へのコルに出る 遠くに雄山 |
 登山道の向こうに龍王岳 |
|
コルに出て右に見えるのが龍王岳で、左に見えるのが雄山である。雄山直下の急登もコルから見るとなだらかに見えるから不思議だ。 ハクサンイチゲやミヤマダイコンソウの咲き乱れる稜線を行くと広場に出る。広場には緑色に塗られた富山大学の観測所があった。カラカラと廻っている風速計が逆に寂しさを感じさせる。 大きな看板か標識があったのだろうか、朽ち果てかけた柱部分だけが残っていた。 |
 昔は立派な標識だったのだろう |
 富山大学の観測所 |
|
龍王岳の手前で道が二手に分かれていた。頂上に向かう道と右に巻く道だ。迷わず頂上への道を選ぶ。 頂上はすぐだった。だがそこから先の道が分からない。道らしきところを辿ったが最後は岩とハイマツに遮られてしまった。 迷ったら戻れ(?)で頂上まで登り返して分岐点まで戻る。分岐点からは巻き道のように見えたがどんどん標高を下げる。頂上から無理して降らず、戻ってよかったようだ。 |
 観測所近くから龍王岳を望む |
 龍王岳頂上(縦走路はないのでいったん戻る) |
|
こちらか側ら見下ろすカルデラは新鮮だった。鍬崎山や弥陀ヶ原からとは見る方向が逆なのだ。カルデラの向こうに弥陀ヶ原大地があり、鍬崎山が浮かんで見える。しばらく見入ってしまった。 急な岩場を降っていくと左側に龍王の東南陵が見えてくる。東陵より難しいとされているだけあって迫力満点である。 とりあえず東陵を制覇してから考えてみよう。 |
 龍王岳よりカルデラを見下ろす |
 龍王岳を南側から見る 右側が東陵 |
|
龍王と鬼の間のコルにはまだ雪渓が残っていて登山道が見えない。稜線歩きだと思って地図を持ってきていなかった。 稜線上には登山道は見あたらない。左の方の支尾根にかすかに道のようなものが見える。双眼鏡を出すがはっきりしない。 たいした距離でもないのでとりあえずそちらに向かった。 |
 今シーズン登ってみたい東陵の奥に雄山 |
 鬼岳 最初の雪渓の左下を歩く |
|
近づいてみると間違いなく登山道だった。鬼岳の東側を巻いているようだ。その支尾根を越えて足が止まった。目の前の雪渓は急で、下方は御山谷に落ち込んでいて見えない。 稜線歩きだと思っていたのでアイゼンもピッケルも持ってきていない。西穂でも思ったが雪渓のトラバースは降りの方が怖い。 悩んだ末、途中の大きな岩まで行ってみることにした。雪渓は表面は腐っているが、すぐ下に凍っている帯が縦に何本も走っている。 |
 二つ目の雪渓を真ん中の岩までトラバース |
 トラバース中に鬼岳を見上げる |
|
ストックでの感触や雪渓の色(白さ)などを頼りに少しずつ斜めに降る。滑ったら止まらないと思うと腰が引けそうになる。 滑っても岩にひっかかりそうな所まで行き、岩に向かって真っ直ぐ降りた。岩の上には鉄の棒やトラ縄が置いてあった。夏道の整備用なのだろう。岩には鎖も張ってあるが雪渓の中に消えている。夏道でも険しそうなことが分かる。 ここで又しばらく悩んでしまった。次の支尾根の登山道の位置が分からない。とりあえずなだらかになっている所までトラバースすることにした。 |
 途中の大きな岩の上には鉄の杭とトラ縄が |
 鎖も何本か取り付けてあった |
|
なんとかこの雪渓のトラバースを終え、次の支尾根の登山道を見つけて曲がり込んだ瞬間、又、足が止まる。 さらに急な雪渓が待っていた。この3番目の雪渓は角度を落とすことなく尾根を巻いて見えなくなっている。 今、ここをなんとか渡りきっても帰りが残っている。帰りの時の天候も不安材料だ。心残りだったが引き返すことにした。 |
 雪渓は御山谷へ落ち込んでいる |
 浄土山の頂上にある雄山神社跡? |
|
今来た雪渓を慎重に引き返す。帰りは登りでもあり、足跡も残っていてそれほど危険だとは思わなかった。龍王岳と鬼岳の間のコルはハクサンイチゲが群生していた。往路で気づかなかったのは心に余裕がなかったからだろう。 朝飯を食べていなかったからか龍王の登り返しは辛かった。登り切った富山大学の観測所前の雪渓でビールを冷やす。 雄山の方から風に乗って人の声が聞こえてくる。まどろんでいる内にしばらく寝てしまった。 |
 雄山にある峰本社より本格的? |
 道を誤り、やっとの事で標識を発見 |
|
12時、浄土山を経由して室堂に降りることにする。浄土山の頂上は観測所から100m程西側で標高差はほとんどない。 その頂上には石垣が残っていた。四辺の一方に高い石積みがあり、その形から昔あった雄山神社跡だと思われる。構造は雄山頂上の峰本社より本格的なようだ。 真っ直ぐに行ったのがよくなかったようで、降りにかかってからハイマツ帯に入ってしまった。方向は室堂に向かっているのだが登山道は別にあるようだ。 神社跡まで戻ってよく見ると南側に角材で作った標識があった。石垣の手前で左に曲がらなければいけなかったようだ。 |
 この下が登山道らしい |
 浄土山から見下ろす室堂平 |
|
しばらく降ると雪渓に出る。ガスで廻りは真っ白だったがここからはもう間違えようがない。左は立山カルデラで右が室堂平だ。足スキーを交えながら気持ちよく降る。 13時、室堂平を横切り、みくりが池へと足を伸ばす。雪渓に囲まれたみくりが池は絵の具をたらしたかのような深い緑色の水をたたえて、そこにあった。 |
 みくりが池とみくりが池温泉(山荘) |
 みくりが池と雄山 |
|
みくりが池を見下ろす高台のベンチでたたずむ。観光客の賑やかな歓声が聞こえてくる。数時間前の鬼岳の雪渓で感じた孤独感とのギャップにとまどう。 そうだった。アルペンルートは標高が高いだけで登山者にはなじめない別世界だったのだった。今更ながらにして思い知らされた。 |
 玉殿の湧水前 |
 立山ケーブルカーのすれ違い |
|
反省その1. 間違えようのない山だと思っても地図は必要だ。今回も何回も惑わされた。 反省その2. 朝食は必ずとること。とらないと午前中でバテてしまう。 |