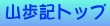| 笈ヶ岳(おいずるがだけ) |
|---|

冬瓜山から望む笈ヶ岳(2006年5月21日撮影)
| 所在地 | 富山県旧上平村、石川県旧吉野谷村、岐阜県旧白川村 | |
| 保護センター前 | アプローチ | スーパー林道 |
| 登山口標高 | 605m | |
| 標 高 | 1841m | |
| 標高差 | 単純1236m 累計(+)1414m 累計(−)190m | |
| 沿面距離 | 片道6.8Km | |
| 登山日 | 2006年5月21日 | |
| 天 候 | 快晴 | |
| 同行者 | 豊本、岸、中嶋 | |
| コースタイム |
自然保護センター(30分)野猿公園(1時間37分)1240mピーク(1時間18分)尾根(50分)冬瓜山(35分)シリタカ山(1時間5分)分岐尾根(30分)笈ヶ岳<休憩1時間5分>(1時間10分)シリタカ(43分)冬瓜山(47分)尾根(1時間10分)1240mピーク(58分)山野猿公園<休憩42分>(20分)自然保護センター 合計13時間20分<休憩約2時間含む> | |
|
富山県には三県にまたがる山が三つある。新潟県と長野県にまたがる三国境(山とは言えない?)、長野県と岐阜県にまたがる三俣蓮華岳、そして岐阜県と石川県にまたがる笈ヶ岳である。 豊本はそれを強く意識しての誘いだったようだ。誘いに乗って金沢の岸、中嶋も参加する。中嶋は4回目の登頂との事。そして唯一の笈ヶ岳経験者である。 |
 白山自然保護センターの前に集合 |
 駐車場の奥が野猿公園への入口になっている |
|
白山スーパー林道料金所の手前、白山自然保護センター前に5時集合。集合場所に遠い者から先に着くのが常で、金沢の2人を待つ。気温は8度。寒い。 10台近い車が停まっていて県外ナンバーも多い。深田久弥が百名山を著してから登り、百名山に入れたかった山だ、と言ったとか言わなかったとかで有名になった山である。 |
 30m程登るとトンネルがある |
 1Km弱で野猿公園に到着 |
|
4人そろい、ゆるりと出発。駐車場の隅から30m程登り、沢の橋を渡って行くと40m近い長さのトンネルがある。真っ直ぐなのでヘッデンは要らない。 さらに沢を越え、歩道用のスノーシェッドをくぐり、だらだらと水平道を行くと野猿公園に着く。公園と言っても東屋のような建物があるだけだった。 その建物の横を流れているのがジライ谷である。漢字で書くと「地雷谷」となるのだろうか? 駐車場から約1Km弱である。 |
 建物のすぐ横のジライ谷を徒渉 |
 600m〜1200mまで急登が続く |
|
岩の頭を拾ってジライ谷を徒渉する。増水時はちょっと気持ちが悪いところだ。渡り終えたところから踏み跡をたどる。 藪こぎを覚悟していたのだが踏み跡はしっかりしていた。ほとんど登山道と言ってもいいくらいである。尾根が細く直登なので自然と急登となる。 途中に高さ10m程の大きな岩があり、岸と中嶋がイレブンだとか3級だとか言っている。岩登りの難易度のようだ。 |
 1240mピークから冬瓜山とシリタカ山が見えた |
 尾根に出る手前の平から白山を望む |
|
標高1200mあたりでなだらかになり一息つく。1240m(?)ピークから少し降ってから、さらに細い尾根を忠実にたどる。 この踏み跡は最近のものではなく、かなり古いと思われる。笈ヶ岳の頂上で発見された経筒に1518年と書かれていたとあるので、その頃からの修験者が歩いた跡かもしれない。、 |
 尾根に出てから冬瓜山に向かって藪漕ぎ |
 冬瓜山頂上直下の急登 |
|
右手前方に冬瓜山の異様な頂上付近が見えてくる。この頂上のナイフリッジが怖くて、北側の冬瓜平を経由するコースが多く紹介されている。そんなことが益々不気味なイメージを強めているのかもしれない。 山毛欅尾山からの尾根に登り切る。ここは視界の悪いときは気をつけないといけない。帰りに真っ直ぐ行ってしまうと山毛欅尾山に向かってしまう。尾根から左に降るところにこれと言った特徴がないので、目印を残しておきたい場所だ。 |
 冬瓜山頂上(1627.9m)の標識 |
 積雪期はナイフリッジとなる細尾根 |
|
冬瓜平には降りずに冬瓜山を越えることにする。しばらくは右に大きな白山を望みながら、快適な雪渓の尾根歩きが続く。 冬瓜山に近づくにつれ、雪渓が切れて藪漕ぎとなる。かすかな踏み跡と赤や黄色のテープを目印に頂上を目指す。 頂上直下は垂直に近かったが、岩や木の根の手がかりが豊富で危険はない。9時15分、冬瓜山の頂上に出る。 |
 この方向から見ると白山は大きな独立峰のように見える |
|
頂上は狭く5人も立てばいっぱいである。露出して倒れかかった三角点が不思議だった。ここから5mぐらい先まで幅40cm程の両側が切れ落ちた岩場となっている。積雪期にナイフリッジとなるところだろう。 雪がなければ特に危険というようなところではない。その細尾根を渡ったところにもう一つ三角点があった。普通の三角点ではなく、一等とか二等と書かれている場所に次という字が書かれている。次三角点とは? |
 倒れかかっていた冬瓜山の三角点 |
 もう一つあった「次?三角点」とは? |
|
そこから次のピークは右側を巻く。巻くとすぐに雪渓があり、なだらかに降る。降ったあとは、当然ながらシリタカ山への登りとなる。 最近のトレーニング不足がたたり、このあたりからバテてくる。9時50分、シリタカ山の頂上を踏む。 頂上から仙人窟へ分岐している小ピークが見えた。急登のピーク手前は雪渓が切れている。左斜面をトラバースしている先行者がいるので、跡をたどることにする。 |
 頂上からはこの岩の左を巻いて降った |
 冬瓜山を降り、シリタカ山を目指す |
|
最低鞍部まで120m降り、分岐のピークに向かって左斜面をトラバースする。上部は雪が硬く、滑ったら止まれそうもなく気持ちが悪かった。 トラバースを終えてからピークに向かって雪渓を直登する。最後にピークを10mほど藪漕ぎっして仙人窟岳からの尾根に合流した。 そこから頂上まで、東側にびっしりと雪渓が残っていた。小笈ヶ岳(1800m)を越え、頂上直下の藪を登り、11時25分、頂上に立つ。 |
 シリタカ山から冬瓜山を振り返る |
 シリタカ山から笈ヶ岳を望む |
|
頂上は灌木もなく360度の視界が広がる。北には大笠山が見え、その右奥に見えるのは赤摩古木山だろうか。 東の三ケ辻山や人形山の後ろに北アルプスが広がる。毛勝三山から剱、立山、薬師、黒部五郎、とつながり、槍に穂高連峰、乗鞍から御岳まで見える。 南には白山が独立峰のようにゆったりと広がる。西に見えるのは大瓢箪山、山毛欅尾山だろうか。だが、その独特の雰囲気で、小さい冬瓜山の方に存在感がある。 |
 仙人窟岳からの尾根との合流点 |
 笈ヶ岳頂上直下 |
|
頂上はそれほど広くなく、宴会が出来るのは15名ぐらいだろう。その一画を借り、いつもの乾杯の儀式。ビールを冷やすための雪をぬかりなく持ち込んでいるのは流石である。 途中でいっしょになったり離れたりしていた単独の登山者が登ってくる。なんと神岡の方だった。青垣さんといい今年初めての山だという。 いきなり笈ヶ岳というのがすごい。流石神岡の方、と思ったのは多分、私だけだっただろう。 |
 山頂の標識と遠くに白山 |
 左から池原、豊本、中嶋、岸 |
|
山頂には三角点の他、木柱や石柱、石仏の入った石の祠がある。さらに蓋のついた大きな缶が二つあり、中には登頂記録が書かれた小さなノートが入っていた。 古い方の缶には名詞も入っていて、パラパラとめくっていると見覚えのある名前が出てきた。いっしょに登ってきた中嶋の旦那さんの名刺だった。 すぐに家に電話を入れていた。せっかくなので記念に山用の名詞を入れさせてもらった。 |
 笈ヶ岳山頂の三等三角点 |
 缶の中に手紙や名詞が沢山入っていた |
|
12時30分、頂上を後にする。早起きとほろ酔いで半分眠りなが、シリタカ山に向かう。この120mの登り返しが辛かった。 冬瓜平経由で帰ろうという案もあったが、降り口が分からず、冬瓜山経由となる。一度歩いた冬瓜山は、単に藪こぎがうっとうしいだけの山となっていた。次回は積雪期に、と思った。 |
 こちらは新しい缶で記録帳なども入っていた |
 中に不思議な石像があった |
|
登るときに少しだけ摘んだコシアブラを探しながら降る。沢山あるのを見ながら登ったのに、なかなか目にとまらない。 それでもいくつか見つけて摘んだ。天ぷらが美味しいという。 |
 頂上を後にして尾根をたどる |
 冬瓜山の登り返しと白山 |
|
1240mピークからは疲れもピークに達し、辛い降りとなる。急降にモモがパンパンになり、ヒザが笑う。 岐阜市からのご夫婦は旦那さんだけ笈ヶ岳に登り、奥さんを待たせておいたそうだが、奥さんの方は急降に手こずっている。明るいうちに戻れるのか心配だった。 5時20分、野猿公園に戻る。若い者に張り合うつもりはないが、岸の強さ(早さ)には脱帽である。彼が単独だったら3時過ぎに戻っていただろう。 |
 冬瓜山の頂上と遠くにシリタカ山 |
 冬瓜山の降り |
|
冬瓜山から飲み水を切らし、ジライ谷で沢水を飲もうと楽しみにしてきたのに、濁っていて飲めない。雪解け水で増水して濁っていた。顔を洗い、うがいをするだけにとどめる。 地図にない踏み跡と藪漕ぎ、そして雪渓をミックスした面白い山だった。登山をスポーツと捕らえている者には楽しめる山だろう。 |
 独特の形をした冬瓜山 |
 野猿公園に戻る(5時20分) |
|
自然保護センターの自販機で買ったコーラで乾杯。ハードな山ほど、降った後の虚脱感(浮遊感?)がなんともいえない。 この山には、又、登りたいと思わせる何かがある。それが何なのかはよく解らない。次回、訪れたとき、それが解るのだろうか? |
 オオカメノキ(ムシカリ) |
 陽光に輝く若葉は生命力に満ちている |
 |