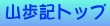| 頸城駒ケ岳 |
|---|

登山口からのぞむ頸城駒ケ岳とバンド(2007年10月13日撮影)
| 所在地 | 新潟県糸魚川市 | |
| 大神堂 | アプローチ | シーサイドバレースキー場から対岸の林道をたどる |
| 登山口標高 | 605m | |
| 鋸山標高 | 1631m | |
| 標高差 | 単純1026m 累積(+)1470m 累積(−)1190m | |
| 沿面距離 | 9Km | |
| 登山日 | 2007年10月13日 | |
| 天 候 | 曇り | |
| 同行者 | ken 、BOW | |
| 参考コースタイム 山と高原地図(旺文社) |
登山口(分)(分)(分)(分)(分)(分)登山口 合計 時間 分<休憩 時間 分含む> | |
| コースタイム | 合計10時間30分<休憩2時間55分含む> | |
|
2003年の11月に駒ケ岳に登り、帰りに梶山温泉に寄った。そのとき鬼ヶ面から降りてきたパーティーを見ていつかはたどりたいと思ったコースだった。 全員ヘルメットを被っていて「ザイルを出したか?」の問いに「出さなかった」が(我々だったから...)のようなニュアンスがあった。 |
 |
 |
|
kenとBOWが梶山温泉に車をデポしたあとシーサイドバレースキー場の前で(大きな登山靴のモニュメントがある所)待っているという。時間は6時半。 ありがたく言うとおりにさせてもらってゆっくり4時半に家を出る。大野のセブンイレブンでカップ麺を買い、朝食にする。 それでも待ち合わせ場所には6時前に着いてしまった。 |
 |
 |
|
車をデポして帰ってきたkenの車で登山口に向かう。対向車が来たらすれ違い出来ないような細い道だ。両側から草も垂れている。 登山口近くでちょっと広い道と交差する。そちらが本来使われている道かもしれない。 |
 |
 |
|
登山口には小屋があり、トイレや水場もある。小屋はともかくトイレと水場はありがたい。7時10分、小屋からちょっと下がった登山口に入る。 雨露の残った下草にパンツの裾を濡らしながら行く。先は長いのでゆっくりペースを作る。途中、山葡萄を見つけ、少しだけ採った。甘くて美味しい。 |
 |
|
最初の水場を過ぎるとすぐに岩壁の下に出る。ここの凹部(ディエードル)は登れそうな気がする。ただ、礫岩なので、つかんだ岩がボコッと欠けるかもしれない。ハーケンも効きそうもない。 |
 |
|
山葡萄を食べながら小休止を入れる。落石の心配があり、休憩場所としてはよくない場所かもしれない。 ここからバンド部分を斜上していく。途中から岩が覆いかぶさってきて天然のスノーシェッドのようになってくる。 斜度もきつくなりトラ縄が張ってある。バンドを抜けたところにも水場があるが、水量は細く飲む気がしない。 |
 |
 |
 |
 |
|
しばらくは急な直登の道が続くが、やがてなだらかになり左下がりのトラバース道となる。ブナの紅葉がきれいだ。 海川からの登山道と合流するとすぐに頂上だ。時間は9時5分。とりあえずの乾杯に、おでんを温める。 |
 |
 |
|
10時、頂上を後にして鬼ヶ面に向かう。左前方に見えるのは双耳峰の阿弥陀岳だ。放山からの眺めとは正反対の方角になる。 100m近く降り、また同じくらい登り返す。このピークからの降りが今回の核心部だった。 |
 |
 |
|
垂直に近い岩場にはクサリやザイルがはってある。腕力が必用で、力のない女性達には辛い降りである。実際BOWはここを降るのに10分ほどかかっていた。 ここを降ってからは鬼ヶ面山の右斜面を行く。 |
 |
 |
|
小さな小ピークを右側から巻く。巻いた後の登りは長いハシゴとなっている。 鬼ヶ面山本峰(北峰)は北にあり、ここも大きく右側から巻いていて頂上は通らない。南峰は登山道から10mほど登れば頂上だ。 |
 |
|
頂上から戻り、左側へと降る。海谷峡谷へ降る道じゃないかと思うくらい降るがまた登りとなる。 そこから標高1400m台の軽いアップダウンを行く。鋸岳への登りにさしかかったところに海谷峡谷への分岐点があった。 |
 |
 |
 |
 |
|
分岐点をすぎたところで2次会。2次会とは言いながらメインディッシュは鰻丼と鍋焼きうどん。結構ヘビーだ。 まー、1次会が軽すぎたせいもある。広場がなかったので登山道で広げた。誰も来ないことを祈った。 |
 |
 |
 |
 |
|
鋸岳は縦走路から50mほど先へと分岐している。14時15分、鋸岳の頂上に立つ。さらにここで3次会を開く。 バーボンを垂らしたコーヒーに果物のタルト。このコースで形を壊さず運んでくれたkenさん、ありがとう。 |
 |
 |
|
縦走路に戻り、分岐から一気に降る。ここは急な岩尾根となっていてフィックスされたザイルがありがたい。 徐々になだらかになって鞍部になったところが三叉路である。真っ直ぐ登っていくと雨飾山へと続き、右に降ると梶山新湯である。 |
 |
 |
|
16時40分、梶山新湯に戻る。2万5千図の登山道とはかなりずれているので、あらかじめGPSにルートを載せていく人は注意が必要だ。 駒ケ岳の登りもバンドあたりからまったく違う。登山道を入れた人は地図を見てイメージだけで書いたとしか思えない。 |
 |
 |
|
このコースは下山口に温泉があるのがいい。夕食時間に近かったせいかお風呂は空いていた。内湯から外の露天風呂へはいつもの「タオル巻いて小走り」で移動する。 露天風呂はひとつしかない。今まで気がつかなかったが混浴なのか分浴なのか不明だ。いつも何気に入っていた。 |
 |
 |
| 玄関が出来たのでよけいにそれが気になる。宿に明記されていないと言うことは当事者同士で話し合って決めてくれと言うことなのだろう。 |
 |
 |