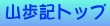| 立山川〜奥大日岳〜小又川 |
|---|

雄山をバックにカガミ谷乗越から奥大日岳にへと向かう(2008年5月17日)
| 所在地 | 富山県上市町 | |
| 馬場島 | アプローチ | 早月川最奥 |
| 登山口標高 | 755m | |
| 標 高 | 2606m | |
| 標高差 | 単純1851m 周遊累積(+)1870m (△)2060m | |
| 沿面距離 | 周遊18Km | |
| 登山日 | 2008年5月17日 | |
| 天 候 | 曇り時々晴 | |
| 同行者 | 長勢、岩城 | |
| コースタイム |
馬場島(1時間15分)毛勝谷出合(20分)東大谷出合(50分)室堂乗越分岐(1時間50分)カガミ谷乗越<休憩30分>(1時間15分)奥大日岳<休憩1時間25分> 奥大日岳(45分)天狗の踊場(40分)右俣出合(12分)大日山谷出合(30分)サンハリ谷出合(28分)コット谷出合(1時間10分)小又川出合 合計11時間10分<休憩1時間55分含む> | |
 奥大日岳から天狗の踊場へダイブしてカスミ谷へ。コット谷出合から小俣川出合までがかったるい |
|
富山県登山条例解禁の第1週、立山川に入った。そのまま室堂に抜けようと思っていたところへ天狗の踊場から小又川に抜ける案が浮かんだ。 馬場島荘で会った嶋田さんから聞いた「カスミ谷経由で天狗の踊場に行ってきました」というのがヒントになった。 |
 |
 |
|
ネットでカスミ谷を調べてみると30m級の滝がいくつかあるらしい。高巻けないとか、ハーケンを打ち込んだとか書いてある。 もしも、雪融けが進んでいたら。ハーネスまで持たなくても、20mザイルとスリングぐらいはいるかもしれない。落石の心配もあり、ヘルメットも持ち込む事にする。 |
 |
 |
|
岩城が同じ日に立山川に入り、室堂乗越をスキーで往復するという。帰りのスピードが違うし、コースも違う。一緒には行けない。 そこへ長勢から参加のメールが来た。単独の心細さが解消され、おまけに小又川に車がデポ出来る。 馬場島まで車道を歩くのは間が抜けていて気がすすまなかった。長勢の説得か、岩城も一緒にスタートすることになった。 |
 |
 |
|
小又川出合5時半の集合に5時前に着いてしまう、2人も5時過ぎにやってきたので、まー結果オーライ。車を1台デポして立山川へ。この時点ではまだ岩城は室堂乗越往復の予定。 林道がユーターンしている地点から先は進入禁止だ。空き地に車を停めて身支度をする。5時45分、出発。 |
 |
|
林道は立山川取水口までだ。昨年の夏はここから左岸を行って敗退した。右岸に歩道(?)があるのを知らなかった。 今回は雪渓が残っていてどちら側でも歩ける。雪渓の厚さも充分で川の上を歩けるところも多い。 |
 |
 |
|
6時半頃先行者4人を発見。右岸の岩を登っている。スキー靴で登りにくそうだ。登り切ったところで追いついた。 なんとEASさんだった。他の3人は労山の尾田さん、山ボーダーさん、いっちゃん。皆、ネットで何となく知っている。 |
 |
|
ここから7人で室堂乗越を目指す。スキー登山の4人はスキーをはいたりぬいだりで遅れ出す。岩城はスキーを担いだままだ。 予定していた天狗の踊場への雪渓に着いたのは8時10分。時間と体力は余っている。そのまま室堂乗越を目指した。 室堂乗越の取り付きまでは斜度も大したことがない。今日は3人とも絶好調でハイペースを保ったまま行く。 |
 |
 |
|
8時50分、室堂乗越手前でコースをカガミ谷に変えた。室堂乗越をショートカットして直接カガミ谷乗越へ向かう。 そんなに急とは思えないがスキー歩行の岩城にはきつかったようだ(約45度)。最初はジグを切っていたスキーをぬいで、担いでしまった。 |
 |
|
9時57分、カガミ谷乗越に出る。雪面ばかり見ていた目に、いきなり広がるパノラマの世界。室堂平から天狗平、手前には称名滝上廊下。うれしいご褒美。 この角度から見るのは久しぶりだ。頭では解っている地形でも実際に見るとまた違う。新鮮だ。 |
 |
|
スキーを担いで、喘いでいる岩城を待って小休止を入れる。ビールを温存してウイスキーの水割りで喉をうるおす。景色もよく、なかなかいい感じだ。 残りの標高差は約200m。時間も充分残している。体力勝負は終わり、残るは奥大日の雪庇、カスミ谷大滝、落石などのリスクだけだ。 |
 |
 |
|
体力勝負は終わったと思ったものの、最後はやはり辛かった。ガスがかかり、方向が定かではなく、雪庇も見えない。ガスがひくのをしばらく待った。 はれた瞬間、方向を見定めて奥大日へと向かう。4mほどの小さなピークを登ったところに奥大日岳の標識があった。時間は11時45分。歩き始めて6時間。 |
 |
 |
|
本当の奥大日岳頂上は通り過ぎてきた稜線にあり、標高は2611mである。夏道はこのピークの南斜面をトラバースしている。 この頂上には「剱岳・点の記」の柴崎芳太郎が1907年に選点造標した三等三角点がある。これを見ようとするとハイマツの藪漕ぎを強いられる。かもしれない。 |
 |
|
迷った末に持ち込んだストーブで暖かいものを作る。今回はアタック登山と、何とかなる登山の中間ぐらいだ。とりあえず何とかなった。 ゆったりくつろいでいるところへ4人パーティーが登ってきた。頂上はいっぺんに賑やかになる。あまり人が集まらない山で会う人達とは気持ちがふれあうような気がする。なんかいい。 |
 |
 |
|
ガスで雪庇の状態が分からず、降り口をどうやって見つけるか悩んでいた。ガスがひいて見てみれば奥大日岳の頂上には雪庇がなかった。 13時10分、頂上からそのまま大谷尾根へダイブ。足スキーで滑ろうとしたら雪が腐っていた。重い雪がゆっくりと表層雪崩を起こす。 岩城が斜めに切り込んだ雪面は全て雪崩れた。(何故か彼はもう立山川に戻る気をなくしていた) |
 |
|
足スキーが出来ないだけでなく、歩くのも大変だった。重い雪に膝までゴボル。ゆっくり流れていく雪面を見ていると自分が山に向かって逆流しているようで気持ちが悪かった。 4人のスキーヤーは行動食だけのようで、すぐに降りてくる。彼らは頂上と天狗の踊場の中間あたりから立山川に降っていった。グッド・ラック! |
 |
 |
|
天狗の踊場は野球場が軽くひとつは入りそうな広さがある。ここは多分、昔、修験者が修行をした護摩平じゃないかと思う。 護摩を焚く石組みや祭壇跡があり、「護摩堂」や「行者溜り」という地名が遺っているという。う〜ん、気になる。 |
 |
|
13時55分、カスミ谷に入る。斜面が変わったせいか雪は硬くなり、歩きやすくなった。岩城も快適に滑っていく。 このあたりは危険なところもなく足スキーを交えながら気持ちよく降る。 |
 |
 |
 |
|
左側からの大きなデブリがあった。カスミ谷の右俣だ。スキーの岩城はこれを越えるのに一苦労していた。うねりが大きくて越えられないのだ。 この谷は奥大日岳へ真っ直ぐに突き上げている。ガスがかかっていて上部は見えない。見えないからか、暗い谷に感じた。 |
 |
|
右俣を越えたあたりから川幅が狭まってくる。右岸が切り立った岩で、左岸も草付きの急斜面。カスミ谷大滝だと直感する。 雪はだっぷりあって滝の形は分からない。滝があるのか、ないのかさえ分からない。安心すると共にがっかりもする。我が儘なもんだ。 |
 |
 |
|
次に左側に現れたのは大日小屋に突き上げている大日山谷だ。こちらは広くて明るい沢だった。残雪期の大日岳登山に使えそうだ。 だが、行ってみて、最後に雪庇が越えられずに敗退ということもあり得る。お薦めは出来ない。 |
 |
|
このあたり、右岸は絶壁になっている。この上はクズバ山のはずだ。落差50mほどの滝も雪融け水を落としている。 サンハリ谷の出合は広く、流れもなだらかで出合という感じがしない。靴を濡らすこともなく徒渉する。 |
 |
 |
|
雪渓も切れ、河原歩きが混じってくる。山ノ神尾根の右肩に大熊山が見えてくると小又川の取水口は近い。 取水口からは林道があり、登山から解放されたような安堵感に包まれる。だが実際は小又川出合まで4Kmの林道歩きが待っている。 |
 |
|
林道を歩きながらギボウシを採った。長勢が美味しいというので、つい...後日談だが、食べて見るとちょっと苦かったが歯ごたえが絶妙で美味しかった。 有毒のギボウシがあるというので手を出さなかった。何処にでも生えていてありがたみがなかったこともある。 |
 |
 |
|
この周遊コースは健脚向きだが面白い。逆回りもありだろう。GPSデーターでは22Kmの距離がある。 標高差は小又川出合からだと1950mで立山川からだと1800mだ。どちらから登るかは性格による。(Mかそうでないか) 奥大日岳でテントを張れば富山市から砺波市、高岡市、氷見市の夜景がひろがり、後ろには山小屋の灯火が光る。最高の夜になるだろう。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |