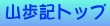ソンボ谷のこと思い出しながら書いて見ます。
私の父親が、笹津ヤキヤマ(八木山?)にあった軍需工場を敗戦で辞めた後、つなぎの仕事としてソンボ谷へ炭焼きに入ったことがありました。
とうじ、私は小学校に通わなくてはならないため、姉と二人で船津のお婆さんの家(父方)に引き取られ、次男(昭和十七年生まれ)と次女がソンボに入りましたので。ソンボは夏休みの間だけでした。
そのころの道は、川伝いに木馬道しかなかったのではないかと思っています。木馬道は知っていますか。木で桟橋を作り、そりに積んだ荷物をロープやワイヤーでで摩擦させながら荷物を降ろすもので木材搬出などに欠かせないものでした。
道も川を遡ったのでなく、西茂住から山越えで行ったように思います。といいますのは、もう80歳に近い従兄弟が母方のお爺さんが死んだ時、それを連絡するため山越えで行ったのを今でも思い出すと今年の年賀状に書いていましたし、中山のほうから歩いた気憶がないのです。
大津山から見て、西茂住のソラの尾根に少しへこんだ部分が峠で道がありました。ここを越えて降りたところに谷が二股になった部分が炭焼きをしていたところです。
その後、昭和40年半ばと思いますが、オートバイを手に入れた記念として、中山からソンボ谷に魚釣りに入ったときは林道がありましたが、舗装も何もなくブルドーザーで押し広げただけの荒れた道路でしたので、途中に置いて登ったように記憶しています。
あとは、昭和31年だったと思いますが、伐採には入っていた木こりが三月末に雪崩四人にやられ、うち一〜二人が死んだように聞いていますので、屋敷跡が残っていればその時分の飯場だったかもしれません。ですから、林道が出来たのは、ブルドーザーが日本の土木工事に使われるようになった昭和30年代半ばに入ってからのことではないでしょうか。
ちなみに、旧の伊西トンネルに到る道路が出来たのは昭和32年ですが、まだ、重機は一切なく、岩を火薬で割るための孔も削岩機でなく、玄翁で鏨を叩いていたので、鉱山の削岩機が凄く近代的に見えた覚えがありましたが、その削岩機も乾式といって水を使って岩粉を出さないのがようやく入り始めたときです。
大体こんなことがソンボの思い出です。しかし、ソンボのことを知っている人と話し合えば、またほかの記憶が出そうですが、またの機会にします。参考になったでしょうか、それともまとはずれ?、、、。
それではまた 静岡 南政雄
追*ニッサンチュウ(西山中)は宮川沿いの山の中で大洞山の西側、旧坂下村、宮川村などを言い、ソンボはそのうちに入らなかったと自分の気持ちでは思っています。
|