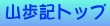| 焼 岳 |
|---|

焼岳南峰より笠ヶ岳をのぞむ 手前は焼岳の噴火口(2009年3月15日撮影)
| 所在地 | 上宝村、安曇村 | |
| 中尾温泉 | アプローチ | 神岡町より車で50分 |
| 登山口標高 | 1190m | |
| 標 高 | 南峰2455m (北峰2399m) | |
| 標高差 | 単純1265m | |
| 沿面距離 | 4.8Km | |
| 登山日 | 2009年3月15日 | |
| 天 候 | 晴 | |
| 同行者 | 山岸、文山、中嶋夫妻、南川夫妻、ken、長勢、岩城、赤坂夫妻、岸、BOW | |
| コースタイム | 中尾登山口(1時間45分)林道終点(1時間10分)アイゼン装着地点<休憩30分>(55分)外輪山縁<休憩30分>(15分)頂上<休憩40分>(3時間5分)林道終点(28分)中尾登山口 合計9時間<休憩1時間40分含む> | |
 |
|
14日に焼岳に登ったあと、中尾温泉に戻って宴会に突入する予定だった。だが天候の都合で宴会翌日の15日が登山日となってしまった。 予想通り、体調不十分で登る羽目になってしまった者が続出する。冬季の焼岳相手ではちょっと辛かった。(と、白状しておこう) |
 |
 |
|
貸し切りのログハウス「ロッジ中尾」をチェックアウトして登山口に向かう。登山口はロッジから車で数分のところ。 8時半、身支度を終え、林道をたどる。せっかく近くに泊まったのに出発が遅くなってしまったが、誰も文句は言わない。言えない。 |
 |
 |
|
登山道へと続く本来の林道から右に分岐する工事用の林道へと入る。白水谷と黒谷に挟まれた北尾根を直登するコースを選んだ。 林道終点からなだらかな樹林帯に入り、20mほどの急登を登り切ると焼岳の溶岩台地末端に出る。ここからアオモリトドマツの樹林帯を行く。 |
 |
 |
|
斜度は徐々に上がり、樹林帯を抜けたあたりでは一歩一歩を踏みしめるラッセルとなる。スノーシューでは辛い斜度になってくる。 振り返った山々は低く垂れた雲に覆われて見えない。目指す焼岳だけが青空に覆われていた。 |
 |
| 前日の下界の雨はここでは雪だったらしい。スノーシューで20cmほどのゴボリ。岸、長勢、岩城がラッセルをリードする。 |
 |
|
斜度が40度近くになってスノーシューの限界か?岩壁に突き当たった、その岩の下の小さな棚でアイゼンに履き替えた。 ここで休憩を取って、いったん全員が集合する。広島から参加した舞ちゃんが辛そう。 |
 このあたりの斜度は45度でスノーシューの限界 |
|
スノーシューをアイゼンに履き替え、ストックをピッケルに持ち替える。気持ちが切り替わるだけじゃなく焼岳の表情も一変する。 ここからは岩と雪のミックスの世界。ちょっとしたミスで命を落とすこともあり得る厳冬期の焼岳となる。 |
 |
 |
 |
|
二日酔いと疲れから注意力が散漫になっているのが分かった。自分の足で歩いているような気がしい。かなりヤバイ状況。慎重に一歩一歩を進めた。 ガスがかかり初め、視界が悪くなってくる。焼岳頂上の見晴らしが気にる。 |
 |
 |
|
いきなり、ふわっと出たところが釜の縁だった。正面に見えるのは焼岳南峰(本峰)のようだ。 北峰の下には黄色の噴煙が上がっている。硫黄を含んだ毒ガスだ。禁止されている南峰より北峰のほうが危なそうだ。 |
 |
 |
|
大きな岩の陰で全員が揃うのを待つ。ここから釜の縁を廻り、南峰へと向かう。南峰には2人の登山者が見えていた。 強風がフリースのセーターを抜けて肌まで届く。我慢できず途中でウインドブレーカー(雨具)を出した。この1枚で寒さから解放される。もっと早く着るべきだった。 |
 奥には槍ヶ岳から奥穂高岳、前穂高岳、明神岳が続き、手前に焼岳北峰が見える |
|
13時45分、焼岳頂上(南峰)に立つ。頂上に見えていた人影は金沢から来た二人組だった。 我々のパーティーにも7名の金沢メンバーがいる。V10(金沢のスポーツジム)の話しなどで盛り上がる。 |
 |
 |
|
ガスがかかったり、ひいたりの中で穂高連峰が見え隠れする。八ヶ岳から南アルプスも見える。流れる雲の合間に乗鞍岳が現れた。 飽きずに見とれていて、ふと気づくと時間は2時を大きく過ぎていた。14時25分、昼食も取らずに頂上を後にした。 |
 |
 |
|
黒谷から見た錫杖岳は笠ヶ岳から続く尾根にしか見えなかった。前衛峰は頂上よりかなり下に位置している。 前衛峰の上の棚から頂上を狙ってみたいと思っていたが、かなり距離がありそうだ。我々では日帰りは無理なようだ。 |
 |
|
帰りは黒谷を降った。来た道は岩と急な斜面で危険な感じがする。未知の沢を降るのは気がすすまないが、とりあえず目先の危険はない。 降るにつれ谷は狭くなり、両方の壁が高くなる。もろい岩肌がむき出しになっていて簡単には上がれそうもない壁が続く。 |
 |
 |
|
わずかに残っていた急な雪渓を登り返すチームと、もう少し下にある登れそうな崖を登るチームに分かれた。広い尾根に登り返して往路のトレースに戻る。 しばらくして雪渓を登り返したチームと合流した。あとは危険なところもなくひたすら降るだけだった。 |
 |
|
林道に戻り、振り返る。焼岳は赤く染まろうとしていた。(望遠で見ると近そうに見えるが実際を遠い) あそこまで行ってきたんだという達成感。体に感じる疲れが心地よい。車に戻った頃、夕闇が迫り始めていた。長い1日だった。 |
 |