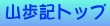| 切雲谷 |
|---|

廃線となった神岡鉄道の鉄橋を使わせてもらった(2010年6月3日撮影)
| 所在地 | 飛騨市神岡町 | |
| 二ツ屋登山口 | アプローチ | 国道41号線二ツ屋 |
| 登山口標高 | 340m | |
| 標 高 | 850m | |
| 標高差 | 単純510m | |
| 沿面距離 | 片道3.2Km | |
| 登山日 | 2010年6月3日 | |
| 天 候 | 晴 | |
| 同行者 | 単独 | |
 戻って流葉の方から林道をたどってみた |
|
国道41号線を南下すると西漆山の南西方向に特徴的な沢が見える。高原川に並行するように走っている。 この沢を地図で見ていて長い間切雲谷と勘違いしていた。高原川との出合で右からの沢と合流しているところもそっくりだったからである。 |
 |
 |
|
家が二軒あったから名付けられたという二ツ屋集落跡(数年前までもう一軒が残っていた)に車を停めさせてもらって廃線となった神岡鉄道の鉄橋に向かう。 金網が張ってあり、進入禁止の看板があった。線路跡を歩くのが目的ではなく、川を渡らせてもらうだけと、勝手に言い訳を考えて渡らせてもらった。ごめんなさい。 |
 |
 |
|
越中と飛騨をむすぶ塩の道は5本あった。東から「鎌倉街道」「越中東街道」「越中中街道」「越中西街道」「「二ツ屋街道」である。 高原川の右岸にあったのが東街道で左岸にあったのが中街道。西街道は宮川沿いにあり、二ツ屋街道は八尾を経由していた。鎌倉街道が一番古く、有峰〜山之村を経由する山道であった。 |
 |
 |
|
橋を渡るとすぐに山へと向かう道があった。これを20m程登ると石垣に出くわす。どう見ても屋敷跡だ。 2〜3軒が建つには充分な広さだが家ではなく畑だったのかもしれない。1999年に発刊された「定本 鰤街道」には二ツ屋から対岸の畑への「渡しの籠」の写真(明治20年撮影)が載っている。 |
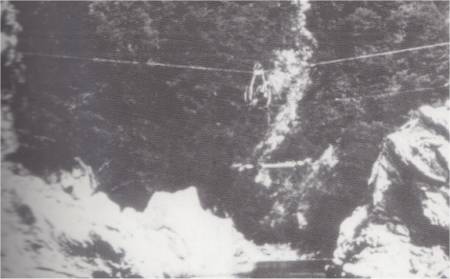 |
 |
 |
|
屋敷跡のようなところから上流、下流の両方に道が延びている。越中中街道の名残なのか? これを上流に向かって(左側に)たどる。道幅は狭く、人1人がやっと歩けるくらいの幅しかない。 |
 |
 |
|
道なりに歩いて沢を登ったのが失敗だった。たどったのは切雲谷の右にある、もずも谷だった。 沢歩きと言うより藪漕ぎに近かった。ま〜、標高の低い沢はこんなもんかもしれない。 美味しそうなヨシナ(ウワバミソウ)を見つけ、熊の足跡も見つけてしまい、沢登りを山菜採りに切り替える。 |
 |
|
車までもどり、切雲谷の上流にまわってみることにした。流葉スキー場から切雲谷に林道が延びている。 峠を越えて降って行くと大洞山への分岐でクサリがはってあった。鍵は外されていたがここまでとする。 |
 右上に斜上している中街道が分かるでしょうか? |
|
越中中街道は高原川の左岸にあった西茂住や西漆山の集落のために必用だった。 封建時代には軍事上の理由で架橋の嘆願はいつも却下されたのだという。住民にとっては迷惑な話だ。 |
 |
|
この中街道にも色々な伝説があるが、史実らしいのは芭蕉の弟子の野沢凡兆が通ったことである。西茂住の南側に凡兆岩があり、この岩に凡兆が詠んだ歌が残っていた。 子供の頃には見えていた道跡も凡兆岩も今は分からなくなってしまった。 |
| 杖石偵察 |
|---|
|
杖石登攀の一番のネックは地権者と地元の人達の理解(許可)だった。神岡の魔女からは(役場の関係者に聞いたらしく)「登ってもいい」と許可をもらっていた。 直接集落の人に会って許可をもらいたかった。この日、集落を訪れると一軒の家(坂本家)に人がいた。集落の長老のような雰囲気があった。 頂上の祠は長倉集落で管理しているとの事。「土地は集落のものだから国のものだ」と言う言葉は意味が不明だったが、許可をもらえた。 「今まであんなところを登ろうなんていう人はいなかった。気をつけて登られ。」との事だった。 |
 |
 木の茂っているところを利用すればワンピッチで登れるかもしれない |
 ちょっとかぶっているところがあるので核心部か? |
 バンド部分でワンピッチをきるか? |
 岩はもろそうでリスも少なくハーケンが効かないかも |
 |
 |